もぐらを飼えるのか――珍しい生態に惹かれて抱く疑問は自然なものです。本記事では、まず「もぐらを飼うのは違法か」という法的な論点を整理し、続いて生態と生活リズム、好む餌と食性、飼育に必要な環境や設備、さらに寿命や繁殖の特徴までを順を追って解説します。
あわせて、飼育に関する具体的な規制や、家庭での飼育が難しいとされる理由もわかりやすく示します。そのうえで、もぐらを保護するための考え方を紹介し、動物園での観察や痕跡観察など、現実的に楽しめる代替方法も提案します。検索の意図にしっかり応えられるよう、実情と選択肢を丁寧にお伝えします。
この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。
- 違法性や許可の要否を理解し、法令違反を避ける
- 生態と食性を把握し、飼育の難易度を現実的に判断する
- 家庭での環境再現がなぜ困難かを具体例で掴む
- 合法かつ現実的な観察・学習の代替手段を知る
もぐら 飼うときに知っておくべき基礎知識
・もぐらを飼うのは違法?
・もぐらの生態と生活リズム
・もぐらが好む餌と食性
・飼育に必要な環境と設備
・もぐらの寿命と繁殖の特徴
もぐらを飼うのは違法?

日本に生息する野生のもぐらは、鳥獣保護管理法の対象とされており、個人が捕獲や飼育を行うためには、原則として自治体からの許可が必要です。無許可で捕獲した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、違法に捕獲されたもぐらを飼育したり譲渡したりする行為も、同様に処罰の対象となります。これは地域の生態系を守るための重要な規制であり、軽視できない内容です(出典:環境省「鳥獣保護管理法について」https://www.env.go.jp/nature/choju)
また、動物愛護管理法では、人が占有する哺乳類は「愛護動物」として扱われ、虐待や不適切な飼育、遺棄などに対して罰則が規定されています。つまり、もぐらを違法に捕獲・飼育した場合は、鳥獣保護管理法と動物愛護管理法の両面から法的リスクを抱えることになります。このように複数の法令が関わる点を理解し、安易に「飼ってみたい」と考える前に、必ず法的枠組みを確認することが求められます。
もぐらの生態と生活リズム

もぐらは、地下生活に高度に適応した哺乳類です。特徴的なシャベルのように発達した前肢を使い、複雑に張り巡らされたトンネル網を掘り進めます。トンネルには役割があり、浅い層に広がるものは主に採餌用、深い層にあるものは休息や繁殖用とされています。これにより、食物資源の効率的な探索と、外敵や環境変動から身を守る仕組みが成立しています。
視力は退化傾向にある一方で、嗅覚や触覚が非常に優れており、土中で微細な振動や匂いを感知して獲物を探します。地上に出ることはほとんどありませんが、完全にゼロではなく、特に繁殖期やトンネルの維持管理の際には短時間だけ姿を現すことがあります。しかし地上は乾燥や高温、外敵のリスクが大きいため、もぐらにとって極めて危険な環境です。こうした生態的特徴は、飼育環境の再現を非常に困難にする要因のひとつです。
もぐらが好む餌と食性

もぐらの主食はミミズや昆虫の幼虫などの動物質であり、完全な肉食傾向を示します。その代謝は極めて高く、数時間でも餌を取らないと衰弱してしまう可能性があると報告されています。観察事例によれば、1日に自分の体重に匹敵するほどの虫を捕食する場合もあるとされており、飼育下でこの量を安定的に供給することは非常に難しい課題です。
さらに、餌は単に「与える」だけでは済まず、常に新鮮な状態を保つことが不可欠です。冷凍や乾燥した昆虫は、必ずしも栄養的に十分ではなく、嗜好性も低いため、自然環境と同じ質の餌を用意する必要があります。これは飼育者にとって大きな負担となり、飼育を継続する現実的な難しさにつながります。
給餌の現実的な難しさ
もぐらを安定的に飼育するうえで最大の課題は給餌です。単に餌の量を確保すればよいのではなく、質や環境条件によっても摂食行動は大きく左右されます。以下のような要因が難しさを増しています。
- 常に新鮮で適切な餌を確保し続ける必要がある
- 湿度や温度、基材の状態によって食欲が変動しやすい
- 餌の保管や衛生管理の負荷が大きい
これらは研究機関や専門の飼育施設であっても容易ではなく、一般的な家庭環境で長期間維持するのはほぼ不可能に近いと言えます。
飼育に必要な環境と設備

もぐらの飼育を考える場合、最大のポイントは「地下環境をどこまで再現できるか」にあります。自然下では数十メートルに及ぶトンネル網を構築し、その内部で生活を完結させています。そのため飼育下でも、広大で立体的な掘削空間を用意しなければ活動欲求を満たすことができません。
土壌の性質も重要で、通路が崩れにくい粒度や含水率を維持する必要があります。乾燥や温度変動はもぐらの体力消耗に直結するため、恒温で湿度を安定させる設備が必須です。さらに、酸素供給を確保するためには換気システムも欠かせません。これらを満たす環境は、家庭で簡易的に再現できるものではなく、実際には研究施設並みの規模が必要になります。
環境再現の要素
- 長距離の掘削行動を許すレイアウト
- 崩落せず呼吸も確保できる基材設計
- 低照度で温度変動の少ない飼育室
- 水分・排泄物の管理と衛生対策
これらの条件が揃わなければ、もぐらは本来の行動を発揮できず、短期間で弱ってしまう可能性が高まります。
もぐらの寿命と繁殖の特徴

もぐらの寿命は野外では数年程度とされますが、正確なデータは限られています。天敵や環境要因によって寿命が左右されるため、研究者にとっても推定が難しい動物のひとつです。繁殖に関しても不明点が多く、発情期や出産数、育児行動などの詳細はまだ十分に解明されていません。
飼育下での繁殖は、世界的にも事例が非常に少なく、成功例は学術的に大きな意義を持ちます。2023年には、研究機関で同居から出産に至ったケースが報告され、もぐらの繁殖生態を明らかにする手がかりとして注目されました。こうした知見は、野生個体群の保護や生態系理解にもつながる重要な成果です。
もぐら 飼う際の注意点と代替案
・飼育に関する法律と規制
・もぐらが飼いにくい理由とは
・もぐらを保護するための考え方
・もぐらを観察できる代替方法
飼育に関する法律と規制

野生のもぐらを個人が捕獲・飼養する場合、日本では鳥獣保護管理法をはじめとする法令に基づく規制を受けます。各都道府県が定める捕獲許可を得なければならず、特に愛玩目的の飼育は実務上ほとんど認められていません。自治体の公式案内によれば、無許可の捕獲は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があり、さらに違法に捕獲した個体を飼育・譲渡・販売した場合には「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」の対象となります。違法性の判断は捕獲を行った場所(特別保護区・自然公園区域など)や、捕獲・飼養の目的によっても変動するため、個人が独断で実行することは非常に危険です。
また、動物愛護管理法の観点からも、もぐらのような哺乳類は「愛護動物」として扱われるため、不適切な飼育環境や放棄行為は虐待や遺棄に該当する可能性があります。複数の法令が重層的に関わるため、研究機関や教育機関の特別な許可を除き、家庭での飼育は現実的に不可能であると理解する必要があります(出典:環境省「鳥獣の保護及び管理」 https://www.env.go.jp/nature/choju/)。
許可の考え方
- 研究・保全目的など厳格な要件を満たす必要がある
- 個人の愛玩目的は実務上ほぼ認められないと考えられる
- 手続きや管理体制、専門知識の裏付けが求められる
もぐらが飼いにくい理由とは
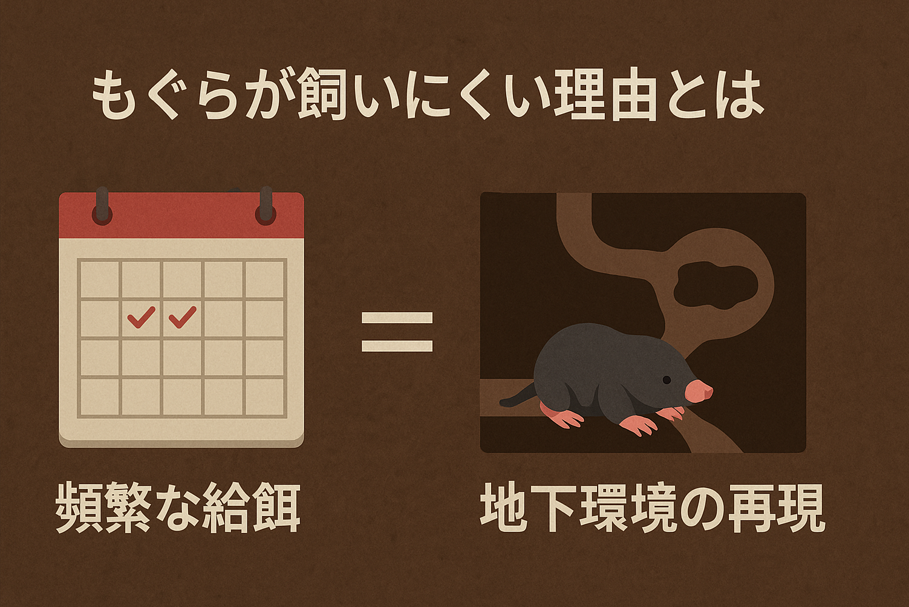
もぐらを飼うことが極めて困難とされる背景には、複数の生理学的・生態学的要因があります。第一に代謝率の高さが挙げられます。もぐらは小型哺乳類の中でも特に基礎代謝が高く、体重のほぼ同量に近いミミズや昆虫類を毎日必要とするといわれています。そのため数時間以上の絶食が致命的なストレスや衰弱につながり、安定した給餌を一般家庭で実現するのはほぼ不可能です。
第二に、地下トンネルの環境再現の難しさがあります。もぐらは1日に数十メートルに及ぶ掘削行動を行い、トンネルの中で温度・湿度・酸素濃度を一定に保ちながら生活します。これを再現するには、膨大な土壌量と長尺の飼育設備に加え、粒度や含水率といった土壌物性の継続的な管理が欠かせません。
第三に、行動特性として縄張り意識が非常に強く、同種個体との同居がストレスや闘争を招きやすいことが挙げられます。加えてストレス耐性が低いため、わずかな環境変化や人為的接触が健康悪化に直結します。これらの特性は動物園や研究施設においても大きな課題となっており、一般家庭の飼育環境との間には大きな隔たりがあります。
もぐらを保護するための考え方

もぐらを保護するために最も重要なのは、直接的に飼育することではなく、生息環境そのものを守ることです。モグラ類は地中生態系の一部を担っており、土壌を耕し通気性を高めるなど、間接的に他の生物や植生の維持に寄与しています。そのため、農地や庭での被害対策では、殺処分に頼るのではなく、忌避剤や物理的な侵入防止ネットといった非致死的手段を選ぶことが望ましいとされています。
また、地域の自然史博物館や動物園が実施する調査・展示・啓発活動に参加することで、正しい知識を学びつつ保全意識を育むことが可能です。学術的・教育的観点からの理解を深めることこそが、長期的にモグラを守ることにつながります。
もぐらを観察できる代替方法

直接飼育する代わりに、合法的かつ安全にモグラを観察できる方法はいくつか存在します。代表的なものが東京都の多摩動物公園における展示です。同園は国内で継続的にモグラ類を飼育・展示してきた唯一の施設であり、地下行動を観察できる専用展示室を整備してきました。展示は個体の健康状態や繁殖状況に応じて変動するため、来園前に公式サイトで最新情報を確認しておくことが推奨されます。
さらに、身近な環境でも「モグラ塚」と呼ばれる盛り上がった土を観察することで、生息の痕跡を実感することができます。この場合も採集や捕獲を伴わないことが重要です。また、学術書籍や動物園・研究機関の公式サイトから体系的な情報を学ぶことで、より深い理解を得ることが可能です。
以下の表は、現実的かつ合法的にモグラを観察・学習できる手段を整理したものです。
| 方法 | 概要 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 動物園展示(多摩動物公園など) | 飼育個体の行動や解説を見学 | 安全で教育的な情報が豊富 | 体調や季節で展示休止あり(参考: 東京動物園協会公式サイト) |
| 痕跡観察(モグラ塚) | 庭や公園で痕跡を観察 | 生息の有無を実感 | 採集や捕獲は行わない |
| 書籍・学術資料・公式サイト | 生態や保全情報を学習 | 体系的・信頼性の高い知識 | 情報の更新時期に留意 |
| 企画展示・講座 | 専門家の解説を聞く | 最新トピックを学べる | 開催頻度や会場に制約 |
注目すべきトピックとして、多摩動物公園では2023年にアズマモグラの飼育下繁殖が世界で初めて確認されたと公表されています。これは野生下で解明が難しい繁殖生態の研究に大きく貢献する成果であり、今後の展示や教育活動の広がりにも期待が寄せられています。
まとめ|もぐらを飼うことを考える前に
この記事のまとめです。
- 無許可での捕獲や飼育は罰則対象となり法令遵守が最優先となる
- 地下生活の完全再現と頻回給餌が必要で家庭飼育は極めて非現実的
- もぐらの生態は嗅覚と触覚に依存し広大なトンネル網を形成して生活
- 主食はミミズや昆虫であり安定供給の難度が非常に高い点が課題となる
- 短時間の餌切れや環境変動が個体に致命的ストレスを与える可能性が高い
- 強い縄張り性と著しいストレス耐性の低さが飼養を著しく困難にしている
- 飼育設備には基材選定や通路設計・微気候制御など多数の要件が必要になる
- 法令上の許可は厳格であり愛玩目的での飼養は実務的にほぼ不可能とされる
- 動物愛護管理の観点からも適切でない飼養は避けることが強く求められている
- 学術的には飼育下での繁殖成功例が近年報告され世界的にも注目を集めている
- 展示は季節や個体の体調に左右されるため事前に最新情報の確認が有効である
- 動物園展示や専門講座・学術資料による学習が現実的で有効な代替手段となる
- 庭や畑での被害対策は非致死的な方法を優先し共存を目指す姿勢が重要である
- 違法性のリスクを避けるには独断での捕獲や飼養に決して手を出さないこと
- もぐらを飼うよりも合法で持続可能な観察や学習方法を選択する価値が高い









