夜になると天井から聞こえるカサカサ音や、どこからか漂ってくる異臭に不安を感じた経験はありませんか。
そんなとき、ネズミが屋根裏で何かしてるのだろうと疑問や不安に思う方は多いものです。
ネズミは屋根裏で何をしているのか、なぜそこに巣を作るのか、その活動内容や時間帯には明確な理由があります。
本記事では、ネズミが屋根裏にいることで発生する被害や侵入経路、鳴き声や足音の特徴まで詳しく解説します。
また、自分で行える駆除方法や効果的な道具、プロに依頼するべきケース、再発を防ぐための予防策なども紹介しています。
屋根裏にネズミがいるかもしれないと感じている方にとって、今すぐ役立つ情報を網羅していますので、ぜひ最後までお読みください。
この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。
- ネズミが屋根裏で活動する時間帯や行動の特徴
- 屋根裏を巣作りの場所に選ぶ理由
- ネズミの侵入経路や屋内への入り方
- 発生する被害とその対処・予防方法
ネズミは屋根裏で何してるのかを徹底解説
屋根裏でネズミが活動する時間帯
ネズミが屋根裏で巣作りする理由
屋根裏のネズミはどこから侵入する?
ネズミが屋根裏にいると発生する被害
ネズミの足音や鳴き声の特徴とは
屋根裏でネズミが活動する時間帯
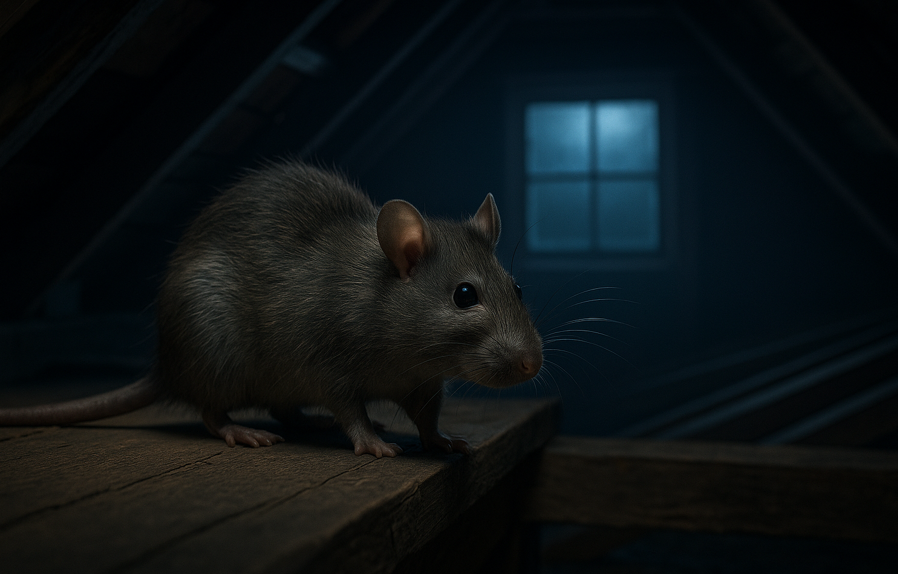
ネズミは主に夜行性の動物であり、屋根裏で活発に動き回る時間帯は夕方から明け方にかけてです。
日中は比較的静かに過ごしており、人が活動する時間帯には姿を見せない傾向があります。
そのため、昼間は屋根裏が静かで、ネズミの存在に気づきにくいことも多いです。
暗くなると、ネズミは食べ物を探しに動き出します。
特に深夜から早朝にかけて、天井裏から「カサカサ」「ドタドタ」といった足音や物音が聞こえてくる場合、それはネズミが活動しているサインです。
この時間帯に音が集中するのは、彼らが危険を避けるために人目につかない時間を選んで行動しているからです。
また、ネズミは一晩のうちに何度も巣とエサ場を往復することがあり、その際に天井裏を移動して騒音を立てます。
こうした行動パターンを把握しておくことは、対策を講じる際にも非常に重要です。
たとえば、トラップを設置する場合、夜間の活動に合わせて仕掛けると効果的です。
つまり、屋根裏でネズミが活動するのは主に夜間であり、騒音や被害に悩まされるのは多くの場合この時間帯となります。
ネズミが屋根裏で巣作りする理由

ネズミが屋根裏を巣作りの場所として選ぶ背景には、住環境としての「静けさ」「保温性」「安全性」という3条件が整っていることが挙げられます。
屋根裏は居住空間と断熱層に挟まれた閉鎖的な空間で、人の動線から外れやすい構造です。
とくに木造・軽量鉄骨住宅では、小屋裏の空気層が熱を蓄えやすく、外気が0~5℃程度の冬季でも内部が10~15℃ほど高く保たれることがあります。
温度変動が緩やかで乾燥しやすい環境は、体温維持にエネルギーを割きたくない小型げっ歯類にとって効率的で、休息・出産・育仔に適しています。
屋根裏は家の中でも人の出入りが少なく、ネズミにとっては安全な隠れ家になります。
このような人為的攪乱の少ない空間では、学習による警戒心の形成が遅れ、行動範囲(ホームレンジ)が屋内配管や電線ダクト、梁上を軸に安定しやすくなります。
加えて、屋根裏は外敵(イタチ類、ネコ、猛禽など)に視認されにくく、嗅跡も拡散しづらいため、外敵回避の観点でも合理的です。
侵入経路は、屋根材の合わせ目、軒天換気口、配管・電線の貫通部などの「隙間」で、ハツカネズミであれば直径6~7mm程度、クマネズミであれば10~12mm程度の孔でも通過可能です。
こうしたサイズの開口は住宅では見落とされがちで、定期点検をしない限り長期間気づかれないことが多いのが実情です。
また、屋根裏には外気の影響が少なく、冬でもある程度の温かさが保たれています。
とくに日射で暖められた屋根面近傍や、浴室換気ダクト・給気ダクト・ダウンライト周り、天井裏配線のトランスや分電部の近傍は微弱な放熱が継続し、周囲よりも局所的に温度が高い「マイクロハビタット(小さな生き物たちが利用する特殊な微環境)」になりやすい領域です。
さらに、巣の材料になるものが豊富なのも屋根裏の特徴です。
古新聞、布切れ、段ボール、ビニール片、そしてグラスウールやセルロースなどの断熱材繊維は、細断して絡めることで保温性と弾力性に優れた「ボール状の巣(直径10~20cm程度)」を作りやすく、産仔直後の保温・保湿に有利です。
セルロース系断熱材は吸湿性が高く、尿や体液を保持しやすいため、嗅跡の固定化と帰巣性の強化にもつながります。
巣材の集積は短期間で進むため、気づいた時点での物量は必ずしも滞在期間と比例しません。少量でも早めに撤去・清掃し、再利用を防ぐことが重要です。
こうして考えると、ネズミが屋根裏を巣に選ぶのは非常に理にかなった行動であることがわかります。
加えて、ネズミは繁殖力が高く、ハツカネズミ(Mus musculus)では性成熟が生後約5~6週、妊娠期間は約19~21日、1回の出産で5~6匹前後、条件が整えば年に複数回の出産が可能と報告されています。(出典:University of California Statewide IPM Program『Pest Notes: House Mouse』)
屋根裏の「静かで暖かく安全」な環境は、この高い繁殖特性と相性が良く、短期間で個体数が増えやすい点に注意が必要です。
屋根裏のネズミはどこから侵入する?

ネズミが屋根裏に侵入する経路は複数あり、意外な場所から入り込んでくることがあります。
主な侵入経路としては、屋根の隙間、通気口、壁のひび割れ、配管のすき間などが挙げられます。
わずか2cmほどの穴があれば、成体のネズミでも体を通すことができるため、建物の外壁に小さな穴があるだけで侵入されるリスクが生じます。
屋根瓦のずれや外壁との接合部にある隙間も見逃せません。
特に古い家屋では、経年劣化により建材がゆるみ、ネズミが出入りしやすい状態になっていることがあります。
また、エアコンの配管や電線が通っている穴にパテがしっかり詰まっていない場合、そこを通じて屋内へ侵入されるケースも少なくありません。
さらに、下水管や排水溝の周辺も注意が必要です。
ドブネズミは水中を泳ぐ能力があり、下水を通って家の中へと侵入することもあります。
マンションなどの集合住宅では、他の部屋から移動してくるケースも考えられるため、1軒単位での対策が難しい場合もあるのです。
このように、ネズミの侵入経路は多岐にわたるため、屋根裏への侵入を防ぐには建物全体を点検し、わずかな隙間も見逃さない徹底した対策が求められます。
ネズミが屋根裏にいると発生する被害

屋根裏にネズミが棲みつくと、さまざまな被害が発生します。
代表的なものは騒音被害、悪臭、建材や配線の破損、そして衛生的な問題です。ネズミはただ居るだけでなく、家の中を破壊したり、人間に健康被害をもたらす可能性もあるため、放置は非常に危険です。
まず、音の被害としては、天井から足音が響いたり、物をかじる音が夜間に聞こえたりすることが挙げられます。
これにより睡眠を妨げられ、生活に支障をきたすことも珍しくありません。
また、ネズミの糞尿による悪臭や汚れも深刻な問題です。
特に屋根裏に巣を作っている場合、断熱材などに尿が染みついてしまい、異臭が家中に広がることもあります。
さらに、ネズミはさまざまなウイルスや細菌を媒介するため、衛生面でも大きなリスクとなります。
そしてもう一つは、建物への物理的被害です。
ネズミは常に歯が伸び続けるため、電気配線や木材をかじって削ろうとします。
この行為により、漏電や火災の原因となることもあります。
このように、屋根裏のネズミが引き起こす被害は多岐にわたり、早期発見と迅速な対処が不可欠です。
ネズミの足音や鳴き声の特徴とは
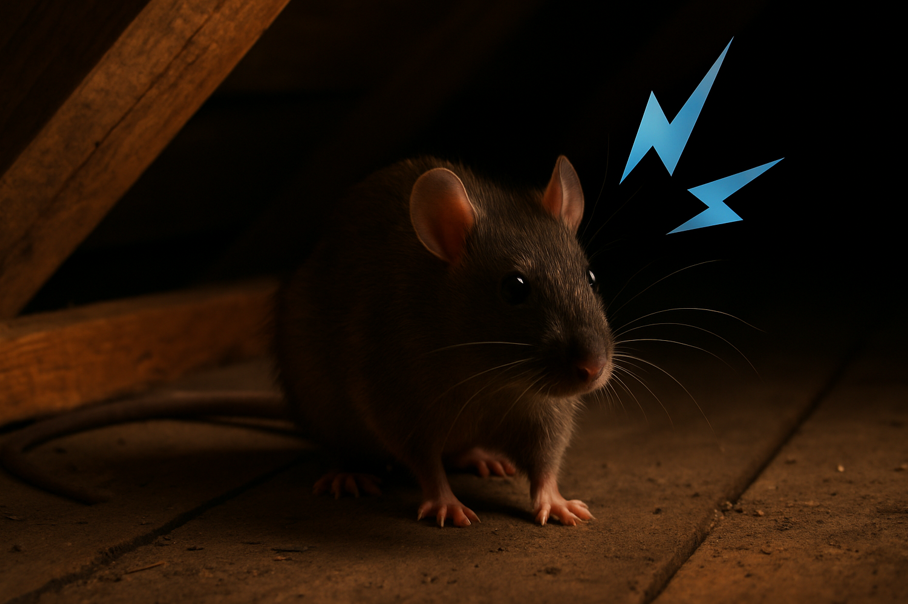
ネズミが屋根裏にいる場合、最初に気づくきっかけとして多いのが「音」です。
足音や鳴き声には特有の特徴があり、それを知っておくことでネズミの存在にいち早く気づくことができます。
ネズミの足音は、「カサカサ」や「トタトタ」といった乾いた音が特徴です。
これは小さな足で軽快に動き回るためで、特に天井板の薄い木造住宅では音が響きやすくなります。
活動時間が夜間であることから、就寝中に足音が聞こえることで不快感を抱く方も少なくありません。
一方、鳴き声はそれほど大きくはありませんが、「チューチュー」といった高い音を発することがあります。
また、威嚇や警戒を示す際には「キーキー」といった少し甲高い音を立てることもあります。
これらの音は複数のネズミが同時にいる場合に特に顕著になります。
また、ネズミは動きが素早いため、短時間であちこちを移動することが多く、音があらゆる方向から聞こえてくるように感じられることもあります。
こうした音の特徴を把握しておけば、早期にネズミの存在に気づき、被害の拡大を防ぐことが可能になります。
いずれにしても、普段と違う音が屋根裏から聞こえてくるようになったら、それはネズミが棲みついているサインかもしれません。
ネズミは屋根裏で何してる?その対処法
ネズミ駆除を自分で行う方法
ネズミ駆除に効果的な道具とは
プロにネズミ駆除を依頼するべき理由
屋根裏のネズミ被害を防ぐ予防策
ネズミ被害の再発を防ぐポイント
ネズミ駆除を自分で行う方法

自分でネズミ駆除を行う場合、まずは「ネズミの種類」と「侵入経路」の把握が出発点となります。
これを理解していないと、どんな対策をしても根本的な解決にはつながりません。
ネズミには主にクマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミの3種類がおり、それぞれ行動範囲や好む場所が異なります。
駆除の流れとしては、第一に「侵入経路の封鎖」です。
ネズミは2cm程度の穴があれば通り抜けるため、建物の外壁や屋根周辺にある小さな隙間もしっかりとふさぐ必要があります。
使用する素材は、金属製のパンチングプレートや防鼠パテなど、ネズミの歯でかじられても破損しないものが望ましいです。
次に、屋内に入り込んだネズミに対して「捕獲」または「忌避」で対応します。
粘着シートやカゴ式の罠は比較的安全ですが、設置場所を誤ると効果が出ません。
ネズミの通り道を見極めて配置することが重要です。
また、超音波や忌避スプレーも市販されていますが、ネズミによっては慣れてしまう場合があり、過信は禁物です。
このように、自力での駆除は計画性と根気が必要ですが、きちんと準備し、適切な手順で行えばある程度の効果は期待できます。
ただし、繁殖が進んでいたり、被害が広がっていたりする場合は、無理をせず専門業者の力を借りることも選択肢に入れておくべきです。
ネズミ駆除に効果的な道具とは

ネズミ駆除に使用される道具にはさまざまな種類がありますが、目的や状況に応じて使い分けることが大切です。
効果的とされる道具には、「捕獲用」「忌避用」「予防用」の3タイプがあります。
まず、捕獲を目的とした道具には粘着シート、箱型の捕獲器、バネ式の罠などがあります。
粘着シートは使い方が簡単で、設置場所を適切に選べば確実にネズミを捕らえることができます。
ただし、ネズミが警戒して避けてしまう場合もあるため、足跡や糞の位置を参考に設置することが肝心です。
忌避用の道具には、超音波発生器や忌避剤スプレーなどがあります。
これらはネズミの嫌う刺激を与えることで寄せ付けないようにするもので、侵入前の予防策としても利用できます。
ただし、ネズミが慣れてしまったり、効かない個体がいたりすることもあるため、定期的な交換や併用が求められます。
さらに、予防として有効なのが防鼠金網やパテなど、物理的に侵入を防ぐ素材です。
特に屋根裏や壁のすき間にはこれらを用いて完全に封鎖する必要があります。加えて、ネズミの通路を封じることで再発防止にもつながります。
このように、ネズミ駆除では複数の道具を適切に組み合わせることが成功の鍵となります。
一つの方法に頼らず、状況を見ながら柔軟に対応することが大切です。
プロにネズミ駆除を依頼するべき理由

ネズミ駆除は自力でも対応可能な部分はありますが、被害が深刻な場合や再発を繰り返している場合には、プロに依頼するのが最も確実です。
なぜなら、専門業者は経験と知識に基づいた対応を行い、被害の根本から解決してくれるからです。
多くの業者は、まず現地調査を行い、ネズミの種類や行動範囲、侵入経路を特定します。
この段階で、一般の人では見逃しがちな小さな穴や兆候も見つけ出します。
その上で、駆除だけでなく再発防止の施工もセットで行うのが一般的です。
また、プロが使用する薬剤や機材は、家庭用のものよりも高性能で、効果が長持ちします。
特に殺鼠剤や燻煙剤の使用には専門的な知識が必要で、誤った使い方をすると健康被害や事故につながるリスクもあるため、自己判断での使用は危険です。
さらに、業者の中には保証制度を設けているところもあり、一定期間内に再発した場合は無償で再施工を行うサービスもあります。
これは、自力で行った駆除にはない大きな安心材料と言えるでしょう。
以上を踏まえると、手に負えないと感じた段階で早めに専門業者に相談することで、時間や労力を無駄にせず、確実に被害を食い止めることができます。
屋根裏のネズミ被害を防ぐ予防策

ネズミ被害を未然に防ぐためには、屋根裏への侵入を物理的に遮断し、環境をネズミにとって居心地の悪いものにすることが重要です。
特に築年数の経過した住宅では、小さな隙間や劣化部分が多く、注意が必要です。
まず取り組むべきなのは「侵入経路の封鎖」です。
屋根と壁の接合部、換気口、配管の通り道など、ネズミが通れる穴を見つけたら、金属メッシュや防鼠パテでしっかりと塞ぎます。
木材やスポンジではかじられてしまうため、素材の選定も重要です。
次に行いたいのは、「食べ物やゴミの管理」です。
ネズミはエサを求めて人家にやってくるため、ペットフードや生ゴミを出しっぱなしにしておくことは非常に危険です。
食品は密閉容器に保存し、ゴミも蓋付きの容器に保管するなど、日常的な衛生管理が求められます。
さらに、屋根裏に不要なものをため込まないこともポイントです。
ダンボールや布製品は巣材にされやすく、ネズミの居心地を良くしてしまいます。
定期的に屋根裏の掃除や点検を行い、清潔な状態を保つことが大切です。
このように予防策を徹底して行えば、ネズミが住みつくリスクを大きく下げることが可能です。
被害が出てから対応するのではなく、日頃からの対策が被害防止には効果的です。
ネズミ被害の再発を防ぐポイント

ネズミ被害を一度解決しても、再発するケースは少なくありません。
そのため、駆除後の「再発防止策」が極めて重要になります。
再びネズミを寄せつけないためには、複合的な対策を継続的に行う必要があります。
まず確認しておきたいのは、駆除後に侵入経路を確実にふさいだかどうかです。
前述の通り、ネズミはわずかなすき間でも侵入可能なため、再発するケースの多くは「入口が残っていた」ことに起因します。
一度の調査で完璧に見つけきれない場合は、定期的な見直しが不可欠です。
次に重要なのが、ネズミにとって魅力のない環境を作ることです。
これはエサになるものを徹底的に管理し、巣材となるものを減らすことにつながります。
例えば、食べ物のカスが出ないように掃除を徹底する、食品をしっかり密閉する、屋根裏や収納スペースを整理整頓するといった日常的な工夫が必要です。
さらに、再発を防ぐには「監視の継続」も欠かせません。
ネズミは警戒心が強く、一度駆除されるとしばらくは姿を見せませんが、隙を見て戻ってくることもあります。
超音波機器や忌避剤を定期的に使用し、活動の兆候がないか目を配ることが効果的です。
このように、駆除後の油断こそが再発の引き金になります。
継続的に環境をチェックし、ネズミが戻ってこないような家づくりを意識することが、再発防止の最大のポイントです。
ネズミは屋根裏で何してるのか まとめ
この記事のまとめです。
- ネズミは夜間に屋根裏で活発に行動する
- 日中は人目を避けて屋根裏で静かに過ごす
- 餌を探すために一晩中何度も移動を繰り返す
- 屋根裏は静かで暖かく外敵も少ないため巣に適している
- 断熱材や布類など巣材が豊富にある
- 屋根の隙間や壁のひび割れから侵入してくる
- エアコン配管や通気口などの穴も侵入経路になる
- ドブネズミは下水管を通じて室内に入ることがある
- 屋根裏のネズミは足音や物音で存在に気づかれる
- 鳴き声は「チューチュー」「キーキー」など甲高い音が特徴
- ネズミは糞尿で屋根裏に悪臭をもたらす
- 電線や木材をかじり火災の原因にもなり得る
- 自力で駆除するには経路の封鎖と適切な道具選びが重要
- プロに依頼すれば再発防止まで一貫対応してくれる
- 被害防止には定期的な清掃と環境管理が効果的
関連記事
- チンチラは猫?ネズミ? 見た目と歴史と混同しやすい理由とは
- ネズミを食べる動物はどんな種類?生態や人間との関係を徹底解説
- 野良猫・飼い猫がネズミを持ってくるのをやめさせる具体的方法
- ネズミに粘着シートから逃げられた時の対処法と効果的な設置法
- ネズミが食べ物ないのに住みつく家の特徴とリスクを徹底解説
- 新築でもネズミが出る原因と侵入経路と効果的な防鼠対策まとめ
- ネズミが出る家は終わり?見直すべき環境と再発防止の具体的方法
- ネズミが走り回る 理由から学ぶ 侵入経路の見つけ方・防ぎ方
- ネズミがかじった跡の袋の素材別の被害と効果的な再発防止方法
- 庭にネズミの死骸はなぜ見つかる?考えられる原因と注意点まとめ
- ネズミはチーズが好きというイメージはなぜ?理由と実際の食性









